
学士課程科目紹介
修士課程科目紹介
S-VYASA大学大学2023年1月行われました DDEコース(旧名)では2020年秋入学の学生18名が学位授与式に臨みました
スクーリング&卒業式 参加レポートはこちら
学位授与式に臨む卒業生ら

学位授与式に臨む卒業生ら

学位授与式に臨む卒業生ら

学位授与式に臨む卒業生ら

同時期に実施されたスクーリング

H.R.ナゲンドラ学長との記念写真

修了生 喜びの声
修了生 喜びの声
修了生 喜びの声
修了生 喜びの声
修了生 喜びの声
修了生 喜びの声
修了生 喜びの声
修了生 喜びの声
修了生 喜びの声
修了生 喜びの声
修了生 喜びの声
修了生 喜びの声
修了生 喜びの声
| Division of Yoga – Spirituality | ビジョン: スピリチュアリティを社会的な科学として成立させる。 使 命: スピリチュアリティの哲学的理解を現代の科学的進歩と結びつけ、インドの伝統的な慣習。 パフォーマンスの背後にある科学を解明し、研究と応用につなげること。 目的: 理論と実践的な授業を通じ、志望者、内なる研究者、スピリチュアル・カウンセラーの知識基盤 を養成する。自己成長のために精神的に親和性の高いキャンパスにし、精神性の実践と推進の ための隠れた潜在能力を表現する。 |
|---|---|
| Division of Yoga – Life Sciences | ビジョン: ヨーガを通じた物質ベースのパラダイムから意識ベースのパラダイムへ 使命: 意識に基づく研究、知識の普及、応用のニーズの促進 目的: 意識フィールドを調査するための新しいパラダイムを導入する。意識に基づくパラダイムの研 究のための新たなツールの開発を支援する。臨床セットアップにおけるバイオエネルギーに基 づく評価を促進するために講座カリキュラムを通じた知識の普及戦略を立案する。微妙なエ ネルギー、原子力エネルギー、バイオエネルギーの相乗効果を追求する。 |
| Division of Yoga – Yoga & Physical Sciences | ビジョン: ヨーガを通じた物質ベースのパラダイムから意識ベースのパラダイムへ 東洋(ヨーガとスピリチュアルな伝承)と西洋(現代科学研究)の最高のものを統合した総合 的な医療システムを開発する。 使命: 人類のより良い健康のために、エビデンスに基づいた研究と教育を通じて、現代医学とホリス ティックな古代医学のシステムを統合すること。 目的: 病気を予防し、ポジティブな健康を促進する。全人的な方法で効果的に病気を治療す るために長期的なリハビリテーションで正常化を引き出す現代の技術と古代の洞察力を 駆使して診断ツールを進化させる全人的な視野、臨床知識、技術を持った医療従事者、救急救命士を育成 する。古代の治癒科学と現代医学の融合を理解し、推進するための研究をする。 |
| Division of Yoga – Yoga & Humanities | ビジョン: 教育を通じて伝統的な価値観を復活させ、深層生態学を推進し、調和と生態学を世界的に発
展させ、理想的な社会秩序を構築し、社会生活に価値観をもたらす。 使命: 文学、スポーツ、芸術、音楽、ダンス、歴史、人類学、占星術の分野において、ヨーギ伝承の全体 的なビジョンとツールをもたらすこと。 目的: 生徒の身体的、精神的、感情的、精神的なレベルでの人格を総合的に向上させることができる |
| Division of Yoga – Yoga & Management Studies | ビジョン: 個人、制度、社会の繁栄と調和のために、経営のホリスティック・アプローチを推進する。 使命: インドの聖典に説かれている経営原則と現代の経営システムを研究教育と訓練を通じて融 合させること。 目的: 個人的、社会的、普遍的なウェルビーイングに基づいた「ホリスティック・マネジメントシステ ム」に基づいた人材を育成する。革新的、包括的、成果主義的な学習原則を通じ、豊かな組織 と健全な社会を創造する明日のリーダーを育成する。経営の新たなパラダイムを切り開くた めに、権限を与えられた個人や機関のネットワークを構築する。 特徴: ホリスティック・システム・オブ・マネジメント(HOLSYM)は、西洋の科学技術と東洋 の哲学の最高のものを組み合わせることにより、進化しています。企業研修プログラムは、ビ ジネスの世界への十分な技術を提供します。 |
○専門的能力
次のうち、一つ以上の専門的能力の基礎を修得することを目指す。
インド思想
インドの思想、思想史を俯瞰出来る能力
インド哲学全般を俯瞰出来る能力
インド思想・哲学の基礎的な教養を身に付けている
ヨーガ
ヨーガ・スートラを説明出来る能力
ヨーガ・アーサナを習得していること
ヨーガ・スートラ、バガヴァッドギータなど基本的古典を俯瞰的に説明出来る能力
マントラチャンティングが出来る能力
サンスクリット語を理解出来る能力
人格向上についてヨーガの果たす役割を理解すること
○一般教養
ヨーガに関する基礎的な知識について説明できる。
インド思想全般に関して理解する。
インド5000年の叡智に裏打ちされた智恵を現代社会に活かし、人類の健康、福祉の向上を果たし、
更に変化を続ける社会に順応し多文化・異文化に関して理解を深め、個人の背景が異なる相手との
相互尊重を図ることができる能力の向上。
自ら主体的に学習の目標を設定し、目標を達成するための計画を立てることができる能力。
○<SVYASA大学が4年制大学に移行への変革>
SVYASA大学が4年制大学に移行しようとしてます
その1つの政策として、2023年8月以降に入学する学生に対しては各年次修了後に証書が授与されます
第1学年全試験合格時- certificate
第2学年全試験合格時 -Diploma
第3学年全試験合格時- Bachelor’s Degree
第4学年全試験合格時-Honours Degree
S-VYASA大学ではWHOが2022年に公布予定の「Benchmarks for Training in Yoga ヨーガ指導のためのWHO指導教育基準」に準じた教育内容となっています。
主訴、既往・現病歴、身体所見の結果を記録する能力、見立ての仕方、診断の理解、及びヨーガ療法介入計画に関する指示と指導(運動、食事、睡眠、人間関係、実習者観察)の概要とその患者・生徒との面接時の記録を残す能力を養う。
ヨーガと心理学における人間全体の正常と異常を理解し、心理学的およびヨーガ的な視点の理解、人格の統合、ヨーガにおける心理社会的な意味合いの理解、ストレス・マネージメント法、自己啓発のためのヨーガ的な生き方とカウンセリング法の習得。
専門的な指導実習、倫理規定遵守、研究のための学習内容
プレゼンテーションとコミュニケーションスキル:ヨーガ技法の指導原理、指導とその指導技法との実践的意味合いを理解する能力の育成。
所見を再評価し、ヨーガ療法介入計画のいかなる修正も記録できる能力;守秘義務、インフォームドコンセント/合意とプライバシーに関わる要求、保険、専門職業賠償責任と法的報告を順守する。
ヨーガ実習の治療的効果と、安全性の問題に対応する手段を標準化する補完的実習の知識を理解し、ヨーガの実習に関連した事故を予防する方法を標準化すること。
症例研究や研究分野の研究調査記録に関する臨床実習の基本的な研究技術と継続的な専門教育。
クライアントと上手に接するための伝統的なカウンセリング技法に精通し、同時にヨーガ的なストレス・マネージメントの考え方と人生の厳しい状況に対処するためのヨーガの諸技法を説明する能力の育成。
学習を深めるために、本校でのスクーリングを実施するほか卒業研究ではインドの本校において研究発表を行い、知識の活用能力、批判的・論理的思考力、課題探求力、問題解決力、表現能力、コミュニケーション能力などを総合する力を実践する。また関係する学術集会に積極的に参画し自己研鑽を重ねられるよう配慮をする。
入学生の声
入学生の声
入学生の声
入学生の声 期末試験を終えて
入学生の声 期末試験を終えて
入学生の声 期末試験を終えて
初年度のシラバスはこちらからダウンロードしてください
2年次のシラバスはこちらからダウンロードしてください
3年次のシラバスはこちらからダウンロードしてください
修士課程1年次のシラバスはこちらからダウンロードしてください
S-VYASA大学は、世界的なヨーガの普及を鑑み、ヨーガを体系的に習得している人材育成を目的に、知識的にも技能的にも今後の社会に求められるバランスの取れた人格を身に付けた人材の育成を目指しています。ヨーガに関わる全ての人が社会に貢献できる人間であってほしいという願いのもとに、すべての人に門戸を開いています。 入学に際しては、志望動機から学習意欲を確認するとともに、大学での学びに必要な思考力・判断力・表現力等を有しているか判定します。入学後、学習を進めていく上では高校卒業程度の基礎学力が求められます。仮に履修の不足分野がある場合や、復習が必要な場合には、入学者それぞれに合わせて補習授業を行い、弱点を補います。 ※当大学の授業はすべてインターネットを介して行われますのでネット環境が必須となります。
応募資格:高校卒業程度の学力があればどなたでも応募出来ます
募集期間 2023年12月1日〜24年2月28日
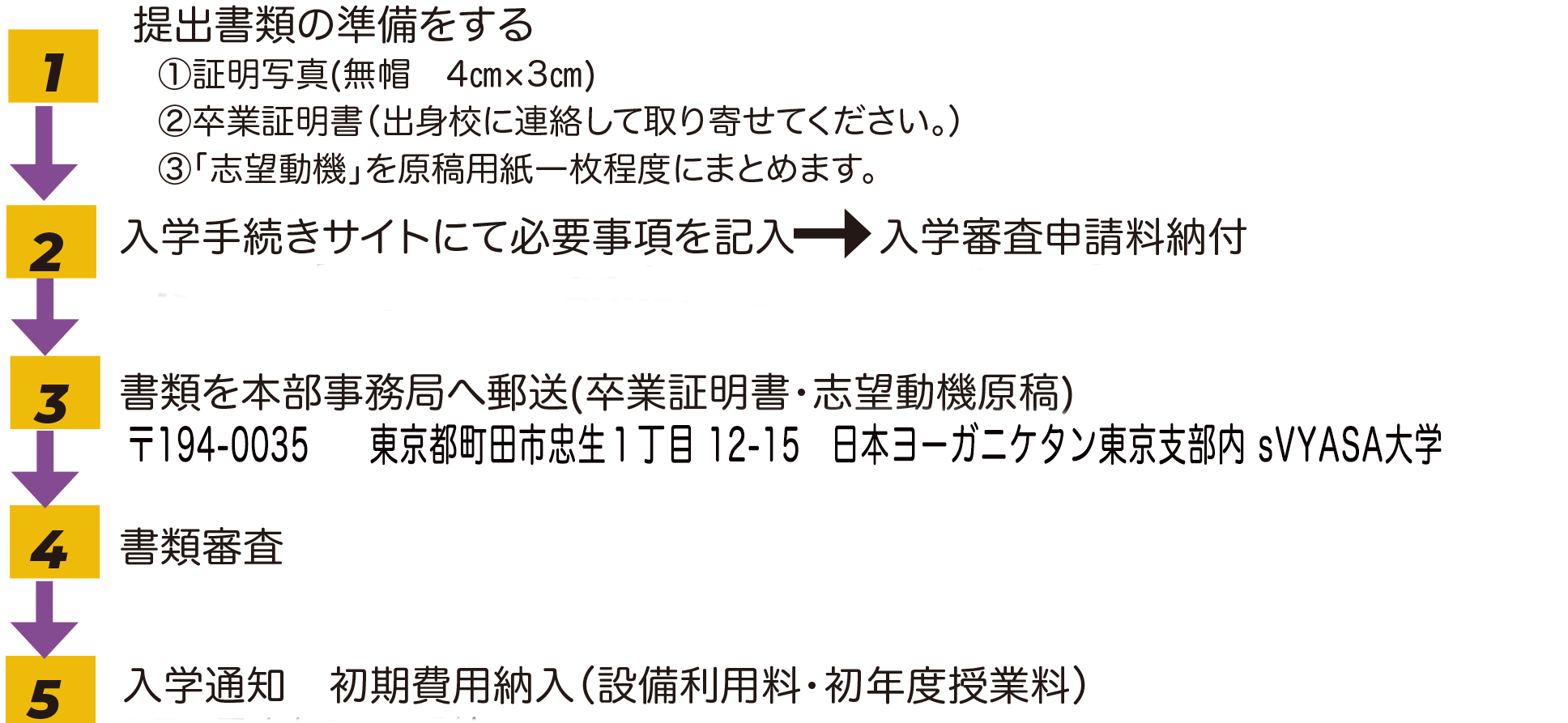
S-VYASA大学日本校では、学生一人ひとりのペースで履修が可能です。 パソコンやタブレット端末、スマートフォンなどでネットに接続することで、そこが学生のキャンパスになります。 本大学では以下の様に期日を定め履修して頂きますが、履修期間内であればいつでも講義動画を視聴出来ます。
前期:9月1日~1月31日(5ヶ月)

(一社)日本ヨーガ療法学会理事長、日本アーユルヴェーダ学会理事、日本ヨーガ・ニケタン代表、(一社)日本統合医療学会理事。スワミ・ヴィヴェーカナンダ・ヨーガ研究所/ヨーガ大学院大学客員教授 シュリシュリ大学客員教授
担当科目 ヨーガ・スートラ YIC
1947年群馬県前橋市生まれ。1969年東京教育大学理学部卒業後、京都大学、インド・マハラシトラ州ロナワラ市カイヴァルヤダーマ・ヨーガ大学で学ぶ。1982年スワミ・ヨーゲシュワラナンダ大師の元で得度。爾来ラージャ・ヨーガとヨーガ療法を日本内外で普及研究。世界保健機構(WHO)“ヨーガ指導基準策定”部会委員。インドS-VYASA大学大学院客員教授。インド・シュリシュリ大学ヨーガ学部客員教授。アジアヨーガ療法会議代表。世界ヨーガ療法連合事務局代表。ヨーガの研究/普及に貢献したとして2019年第1回インド首相賞受賞。

担当科目 基礎医学
1998年 東邦大学医学部卒業
2000年 東邦大学医療センター大橋病院第2麻酔科 助手
2006年 インド・バンガロールにあるスワミ・ヴィヴェーカナンダ・ヨーガ大学院大学博士課程在籍。ヨーガ療法を学ぶ 現在、東邦大学医療センター大橋病院第2麻酔科医研究員一般社団法人日本アーユルヴェーダ学会副理事長、 一般社団法人日本ヨーガ 療法学会副理事長として、日本全国でヨーガ療法士、ヨーガ教師養成に従事。

(ヨーガ行者名:Gautama Muni)
担当科目 ヨーガによる人体システム ヨーガと教育
1959年北海道札幌市生まれ。静岡大学教育学部卒業。その後、日本ヨーガ療法学会理事長、木村慧心氏の元で、ラージャ・ヨーガを習い始める。1984年インド、バンガロールのインド政府公認ヴィヴェーカナンダケンドラ・ヨーガ研究所にて、ヨーガ・インストラクターズ・コース、ヨーガ療法士コース卒業。日本ヨーガ療法学会副理事長、日本アーユルヴェーダ学会チャラカ・サンヒター翻訳委員会委員。現在、ヨーガやアーユルヴェーダ関連文献の翻訳を行なっている。

担当科目 サンスクリット入門 初級サンスクリット語 名古屋市生まれ。幼少より仏像に興味をもつ。1981年名古屋造形短期大学造形芸術学部彫塑科卒業、1991年東洋大学大学院後期博士課程修了(インド大乗仏教専攻、文学修士)、東洋大学非常勤講師。1988年より恩師菅沼晃の「サンスクリット共同研究」に参加、同師のサンスクリット文法書『基礎編』、『実践編』の制作にかかわる。東洋大学にて、「哲学A」「哲学概説」「サンスクリット文献講読」「インド古典講読」を担当。2005年より朝日カルチャーセンター(新宿教室)にて、一般対象のサンスクリット講座を担当。東京都内の高校にて「倫理」の教鞭をとる(2001~2014年)。日本ヨーガ療法学会認定ヨーガ療法士。

博士、公認心理士、臨床心理師、インド中央政府公認ヨーガ療法士 担当科目:心理学 臨床心理学 1981年 高校1年よりヨーガを学び、まもなく指導に携わる。1988年 木村慧心氏(現、日本ヨーガ療法学会理事長)よりラージャ・ヨーガを学び始める。 1990年 インド中央政府公認S-VYASA養成過程修了、ヨーガ療法士。1990年 広島大学大学院学校教育研究科修士課程 修了。2016年 広島大学大学院医歯薬保健学研究科博士課程後期 修了、博士。現在、広島国際大学 学生相談員、広島大学客員准教授。2019年、第25回世界心身医学会(フィレンチェ)においてBest Poster Awardを受賞。 著書 『お母さんと子どものヨーガ』(単著)、A single session of an integrated yoga program as a stress management tool for school employees. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 2016, vol.21 (7) pp.444–449. 他多数 「心理学研究」では心理学の歴史、現代心理学の各分野や検査を紹介し、研究法について講義します。「ヨーガ心理学とカウンセリング」では、インド哲学に基づいた心理療法についても解説します。
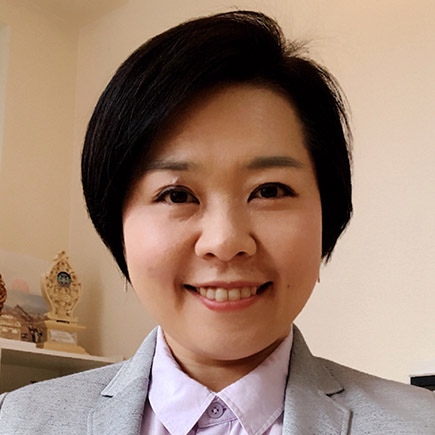
東洋大学大学院総合情報学専攻博士課程後期 ヨーガ療法スタジオぷるなよが 代表 日本ヨーガ療法学会認定ヨーガ療法士 担当科目 統計学 コンピューター 2002年に演劇の勉強で訪れていたアメリカ・ニューヨークでヨーガを心身マネージメントに取り入れ、2005年帰国後、都内と埼玉のヨガスタジオで指導を開始する。2008年(一社)日本ヨーガ療法学会認定ヨーガ療法士になってからは、「ぷるなよが」を設立し、ヨーガ療法指導に力を入れる。2015年埼玉県さいたま市・大宮にヨーガ療法専門スタジオをオープン。一方、ヨーガ療法士となってから国内外の学会へ参加、症例発表を通じ、さらにエビデンスレベルの高い研究をと、2017年東洋大学大学院総合情報学専攻・修士課程に入学、現在は博士課程に進学し、依存症へのヨーガの効果について研究している。講義の内容は、PC操作と統計学の基礎。エビデンスレベルの高い研究には、質的研究(症例など)だけでなく、量的研究も行う必要があるが、そのためには統計を用いる。統計学は難しく思われるが、ヨーガの研究に使える統計を簡単に解説し、使えるようにする。

インドS-VYASA Yoga University修士課程修了 インド政府公認 ヨーガ教師(YCB Level.2) 日本ヨーガ療法学会認定ヨーガ療法士 担当科目 ヴェーディック・チャンティング ハタ・ヨーガ 師の勧めで2015年~2018年の3年間、南インド・バンガロールにあるS-VYASAヨーガ大学院に留学し、ヨーガ・セラピーの修士号を取得しました。修士論文の研究テーマは「ストレスマネジメントとしての瞑想の心理的効果、循環・呼吸器系に与える影響」。本コースではヨーガを様々な角度から学んでいきます。哲学として『ヨーガ・スートラ』やハタ・ヨーガの理論などを学び、ヨーガ・セラピーの観点からは心理学、解剖生理学を学びます。サンスクリット語やマントラを学ぶ授業もあります。それぞれの学びを有機的につなげるためには、次の3つの視点が大事です。①ひとつひとつの科目の理解を深める「木を見る視点」。②学んだことを俯瞰的にみる「森を見る視点」。③学んだことを「どう生かしていくかという視点」。私たち講師は、みなさんの学びをサポートしていきます。
お問い合わせは以下までお願い致します。
090-8866-2514
email:suzuki@yoganiketan.jp